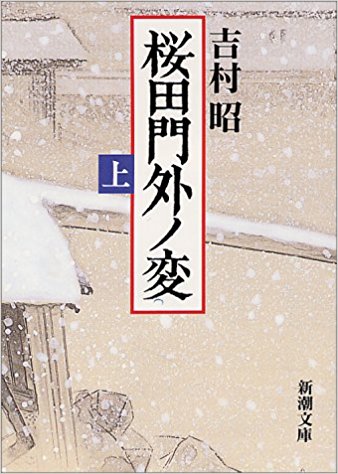
2017.5.5に行った吉村昭さんの『桜田門外ノ変』の読書会の模様です。
私も書きました。
「政治史は、意志の歴史である」
大老 井伊直弼を襲撃した水戸藩士の斬奸趣意書には「外国の圧力におびえた幕府が、不当な条約を朝廷の意向を無視して独断でむすんだことは、国体をそこなう大失態である。」という内容が記されていた。
日米修好通商条約への違勅調印や将軍継嗣問題をめぐって、水戸藩と幕閣老中との対立が決定的になり、井伊直弼による安政の大獄によって、苛酷な政治弾圧が行われた。
この小説の主人公、関鉄之介は、この政治弾圧に巻き込まれ、何かに引きずられるように、桜田門外ノ変の首謀者となる。
ショウペンハウエルの『読書について』には、「政治史は、意志の歴史である」との内容がある。
藩主の命でもないのに、勝手に井伊直弼を暗殺し、その後、逃亡するという主人公の人生は、狂気に近いような意志の力で行われている。
その意志は、水戸藩と朝廷と国体を一本で結ぶ、尊皇攘夷論よって強められていた
そもそも、その尊王攘夷論は水戸学から派生しており、具体的には、藤田東湖と会沢正志斎という二人の水戸学の思想家が主導したものだった。
とりわけ、会沢正志斎は、『桜田門外ノ変』の首謀者に深い影響を与えた思想家で、その影響力は全国にネットワークを形成していた。
関鉄之介ら、『桜田門外ノ変』に加わった水戸藩士の意志を育んだのは、水戸藩の教育である。その核心は、学問としての水戸学であり、政治思想としての尊王攘夷論である。
その政治思想の究極点が、国体主義=超国家主義(ウルトラナショナリズム)だとすれば、実は、このイデオロギーは、現代の日本社会にも潜在している
明治維新の発端となった『桜田門外ノ変』の志士たちの意志は、二・二六事件など、その後の暗殺を伴うような政治的テロリズム通じる意志の表現であるといえる。
『桜田門外ノ変』の水戸・薩摩藩士に、現代の我々が共感するとすれば、それは、政治的意志への共鳴である。
日本の歴史の転回点で不気味に騒ぎ出す、この政治的意志を、近代人の知性によって注意深く見守らなければならない。
(おわり)
読書会の音声はこちらです。
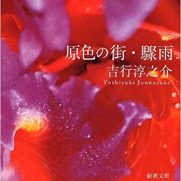

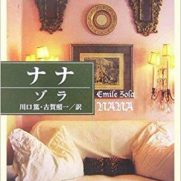
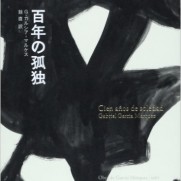
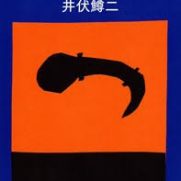

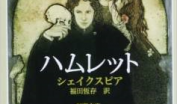
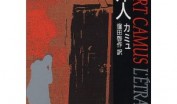
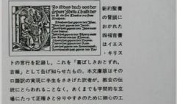
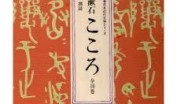

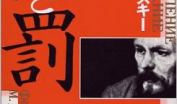
この記事へのコメントはありません。