
『朗読者』ハンナの良心
ベルンハルト・シュリンクの『朗読者』というベストセラー小説がある。
元ナチスの看守だったハンナという36歳の女性と、
ミヒャエルという少年の悲しい恋物語だ。
15歳のミヒャエルが黄疸にかかって道端で嘔吐したのを、
たまたま通りかかったハンナが介抱してくれた。
それを期にふたりの奇妙な関係がはじまる
ふたりは関係を第三者に明かさないまま交際を続けた。
そしてその恋はハンナの突然の失踪によって短期間で終わった。
ミヒャエルは、理由もなく目の前から消えたハンナへの罪悪感に苦しんだ。
自分に落ち度があって彼女を傷つけてしまったのではないかと悩み、
その後の人生において彼は、心から人を愛せない人間になってしまった。
9年後、ミヒャエルは、ナチスの戦争犯罪を裁く法廷で
偶然にもナチスの側の被告人としてのハンナと再会する。
再会しても、彼の心は動じなかった。すでに、彼の心は冷えて、傲慢になっていた。
裁判の過程で、なぜハンナが彼に何も告げずに消えたのかが明らかになる。
ハンナは、文盲であるということを知られたくないから、彼の前から無言で消えたのだ。
そして、彼女が敢えて、ナチスの看守となったのも文盲を隠すためであった。
さらには、ハンナは文盲であることを隠したまま冤罪を受け入れ、無期懲役の刑に甘んじた。
ハンナの文盲の秘密に気づいたのは、この世にたったにひとり、彼だけだった。
「おい、お前は夢じゃないかと、俺は心配なんだ
俺の前にこうして座っているお前は、幻じゃないのか?」
彼(イワン)はたどたどしく(スメルジャコフ)に言った。「私たちの二人のほか、ここに幻なんぞいませんよ。
それともう一人、第三の存在とね。(中略)
第三の存在とは、神ですよ。神さまです。神さまがわたしたちのそばにいるんです。
ただ、探してもだめですよ、見つかりゃしません」(『カラマーゾフの兄弟 下』P291新潮文庫)
第三の存在たる神を見失ったふたりの間には、罪悪感だけが残った。
文盲を克服したハンナは、最期には、自らを裁いてしまう。彼を残して。
(おわり)









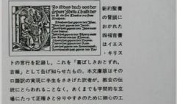
この記事へのコメントはありません。