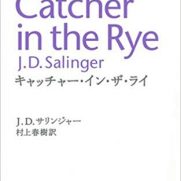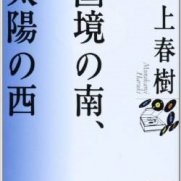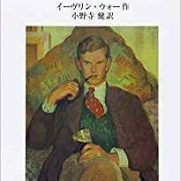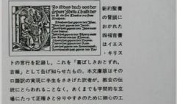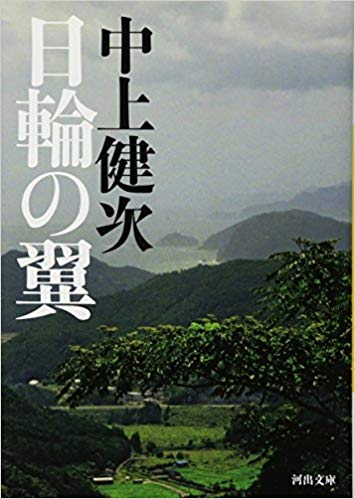
2019.4.12に行った中上健次『日輪の翼』読書会のもようです。
私も書きました。
『罪深い女 罪深い男』
オカイサンを腹に収めて、腹が熱い茶で温って、老婆らは突然、今まで眠っていた天子様と路地のかかわりを思い出す。特にサンノオバは本宮の血を受けていたから、代々天子様の毒味役で、宮中に召されたのが明治の頃まであったのは知っていて、頭の中で畏れ多いと分かっているしそんな事は決してしないと思っていたのに、育つのか育たないのか分からなかった赤子のツヨシに豆や芋を口でかんで擂りつぶして食べさせていたように、天子様たちにも毒味役としてそうしてきた気がしているので、天子様の為ならいつでも矢盾になって犠牲をいとわない誇りがむくむく湧き出てくる。
(婆娑羅-東京)
天子様の毒味役の血を引き継いでいる。路地出身の老婆たちが、天皇と自分を結びつけようとする想像力の働きというのを考えさせられた。紡績工場に就職するはずが、親によって、遊郭に売られるというエピソードが描かれている。頼るものの何もない身も蓋もない環境があって、その環境への適応というのがあからさまに描かれている。
喫茶店で売春するのも、遊郭で稼いだ金を男に貢ぐのも、罪深い行為だ。新約聖書にでてくる罪深い女(マグダラのマリア)を思い出した。罪深さに耐えられず、絶望の際まで追い詰められて、切実な信仰へと向かうという一種の飛躍が、人間の信仰の機縁だとキルケゴールは『死に至る病』で説いている。
自分と社会をつないでいるのは、ロックやルソーなら社会契約である。しかし、オバらと社会は、オバらがでっち上げた欺瞞に満ちた物語によってつながれている。ここで、女性週刊誌になぜ、皇室ネタがいつも掲載されているのか。なんとなくわかる。皇室ネタは、日本の女性のアイデンティティをめぐる想像力を掻き立てるのだろう。高貴な身分だが零落しているという自分と、高貴な身分を、想像の上で貶めたいという背徳感。想像上の二律背反は、切実な信仰への一歩手前にある。
路地のオバらは、路地出身ということと、女性であるということで二重に差別されてきた。罪深さの自覚が、皇居への昂ぶりによって浄化されている。私なりに男としての罪深さを感じることがある。だが、ツヨシには罪に対する反省(想像力)が欠けている。私は、中上健次の描く天真爛漫な男性にリアリティを感じない。
『男性は意志の保持者であり、女性は人類の知性の保持者である』というショウペンハウエルの指摘が作品化されている気はした。
(おわり)