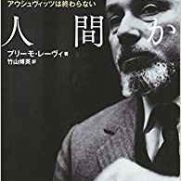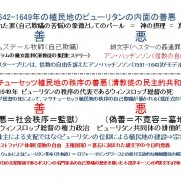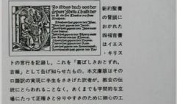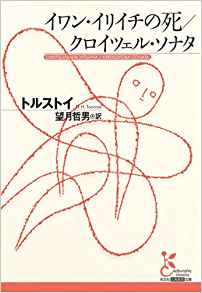
2019.3.15に行ったトルストイ『イワン・イリイチの死』読書会のもようです。
私も書きました。
『ある種の無作法』
2011.3.12の夜中、大きな地震が2回あった。その時、私は、「このまま独りで死ぬんだ」という恐怖を初めて味わった。ジタバタしても、死からは逃れられない、と観念して、そのままかたく目をつむって寝た。幸い、私の住んでいる街は被害もなく、夜が明けるといつもの日常だった。ただ、その日から私の中で「死」という観念が明瞭になった。
トルストイは、ロシア正教の教学を批判して、破門されている。キリスト教では、最期のときに神父や牧師がやってきて、臨終の者のおでこに塗油をして、お祈りをする。『人間の絆』のミスタ・ケアリも、『回想のブライズヘッド』のセバスチャンの父も、最期は十字を切って、苦しみが和らぎ、晴れやかになって、神のもとに召された。しかし、主人公のイワン・イリイチは、信仰が薄く、教会の終油の秘蹟や聖体拝領によって死の恐怖を克服するわけではない。
この作品には、信仰心の薄い、ごく世俗的な人間が、人間の力だけで、死をどう受け入れていくのかというプロセスが詳しく書かれている。彼は死から極力意識をそらすし、周りの人間も、来るべき彼の死を隠蔽する。
死につつあるイワン・イリイチは、病気をおして勤務しても、同情もされず、彼の存在自体が『偶然の出来事』や、『ある種の無作法』のように、取り扱われてしまう。
作品全部を読んで、再度、冒頭を読み直すと、奥さんが年金的なものをもっともらえないか腐心したり、友人たちが、イワン・イリッチの後任人事の話でもりあがったり、通夜の晩に、カードゲームをしたがる様子が延々と書いてあり、グロテスクだ。死につつあるもの孤独と、日常に埋没して、死を避けようとする世間とのやるせない隔絶がある。
その隔絶は、震災から八年経って、世間を見渡したときに感じる隔絶と同じである。私たちの社会も、『偶然の出来事、ある種の無作法』のように、震災を扱っている。
人間だけが、自分たちが死ぬべき存在だと明瞭に意識している。動物は死を避けるだけだ。人間社会において、意識的に死を避けるだけにとどまるなら、我々の精神は、すぐに動物のそれまで退行する。
(おわり)
読書会のもようです。