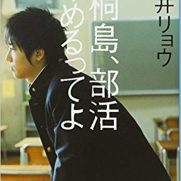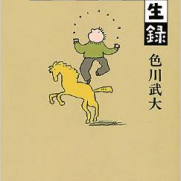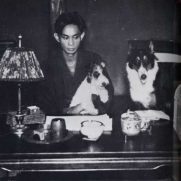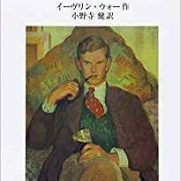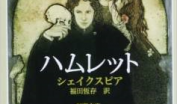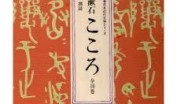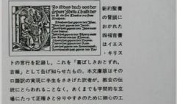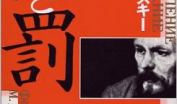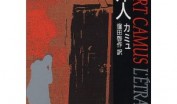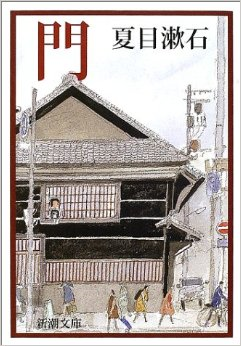
2019.3.8に行った夏目漱石『門』読書会のもようです。
私も書きました。
『道は近きにあり』
『希言自然。(耳を澄ましても何も聞こえないのが自ずから然る道である。)』 老子(第23章)
坂井がポケット論語を読んだ芸者の話をする。その芸者は孔子の弟子では子路が好きだという。(これを機会に私も『論語』をざっと読んでみたが、この挿話は子路ではなくて顔淵の話ではないかと思うので、顔淵の話をするけど……)
顔淵は、孔子の教えを従順に拝聴して、ほとんど忘れて、くつろげるのんきな男だった。その顔淵こそ、『道』を発揮するに十分な器だと孔子は認めた。人間の生み出す知恵は、どれも、所詮は目から入って耳から抜けるような味気ないものだ。一方、宗助が老子に問われた『父母未生以前本来の面目』とは、俗世を遥かに超えて、この世界が現れる前の、名前もない「何か」だ。それを老子は、『道』だという。顔淵には『道』への感性があった。ゆえに、彼は老子のさきがけとなった。
御米と安井との三角関係を気に病んでいる宗助。気に病んでいるのを強いて見せまいと、のんきさを装うが、御米は、宗助の精神状態に感応して具合悪くなるし、小六もへそを曲げる。参禅しても悟ることなく下山する。八方塞がりだ。どこかに『道』があるはずなのに、見つからない。
冒頭、宗助が『近』という字を思い出せないとエピソードがある。
「道は近きにあり、かえってこれを遠きに求むという言葉があるが実際です。つい鼻の先にあるのですけれども、どうしても気がつきません」と宜道はさも残念そうであった。
近代の合理主義は、最短距離で利益を生み出す資本の価値の自己運動だ。『最短距離=近さ』を求めてはいるが、『道』を見失っている。宗助も御米も安井も、否応なしに、資本主義の価値の自己増殖の運動に巻き込まれて、『道』を見失っている。
恋に破れた安井は、冒険者として『道』を求めていたのかもしれない。宗助も、『道』を求めて、『門』をくぐった。『道』のテーマが、『こころ』の先生とKの関係に引き継がれていく。
(おわり)
読書会の録音です。