
2017.2.17におこなったアンデルセンのはだかの王さまの読書会のもようです。
信州読書会のメルマガ読者さんからいただいた感想文はこちらです。
私も書きました。
「はだかではない『かのように』」
はだかの王さまを読んで、森鴎外の『かのように』という短編を思い出してしまった。
皇室の藩屏たる華族の生まれである、明治の青年、綾小路秀麿が、ドイツに留学してプロテスタント神学を学ぶことで、神を『あるかのように』政治的に利用しているヨーロッパ社会の実体と、それに無自覚な日本社会のギャップに悩むという話である。
「自分にふさわしくない仕事をしている人と、バカな人にはとうめいで見えない布なのです。」
どこの国民だって、王さまが「はだか」であることは薄々わかっている。
だが、「王さまがはだかだ」と批判すれば、その批判は、自分に返ってきてしまう。
王さまの近くにいるものほど、『かのように』を信じるふりをしなければならない。
それは藩屏としての義務である。
さらには、私は『かのように』を本気にしてるわけではありませんよ
社会秩序のために信じていますよ。
バカではありませんよ~というふりもしなければならない。
そこで、側近が、白を黒と言いくるめ、偽善を正義と言いくる現象が起こってしまう
国家の権威というものは、煎じ詰めれば、『かのように』で成り立っている。
『かのように』を排して、正直でありたい、無邪気でありたいというのは
子どもと革命家にだけに許されている特権であって、
だいたいの大人は、はだかの王さまがパレードするのを、
国家秩序の安寧である『かのように』支えなければならないのは、
私はしかたないと思う。
『かのように』という態度が、秩序維持のためにはどうしても必要である。
では、外国の詐欺師にダマされて、はだかになっているケースはどうするか?
ダマされた王さまがはだかでもパレードが成り立っていることは大切なことだ。
でも、ダマサれたままでは、たまらない。
『かのように』を『かのように』としっかり認めた上で、
「詐欺師にダマサれている」という受け入れがたい現実に向き合って
どうにか、打開策を探していくしかない。
そのためには、やはり、神学や哲学への理解が欠かせないのである。
(おわり)
読書会のもようです。
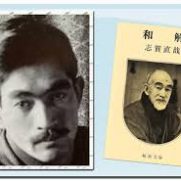
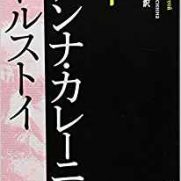

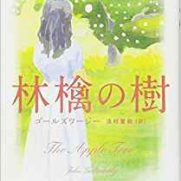
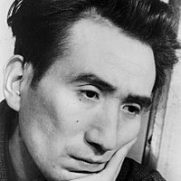
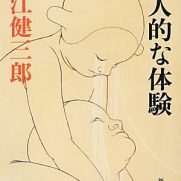
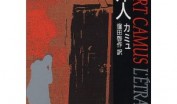

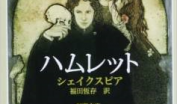
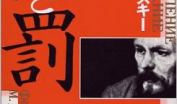
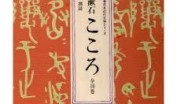
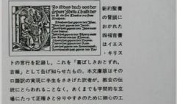
この記事へのコメントはありません。