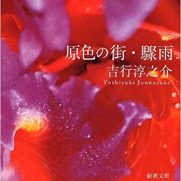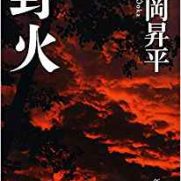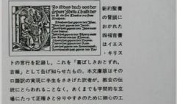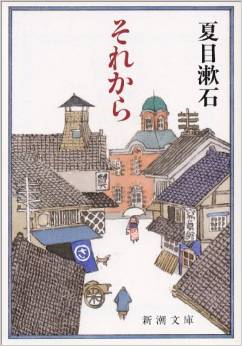
2018.12.7に行った夏目漱石『それから』読書会のもようです。
『代助の自由』
『菊と刀』によれば、日本の家長は、資産の管財人である。
家長はむしろ、物心両面の資産を管理する管財人に近い。その資産は、家族全員にとって重要である。家族はみな、その資産から生じる要請を優先し、個人の意志を二の次と考えるように求められる。(『菊と刀』 光文社古典新訳文庫P.98)
代助の独身も、家長が管財する資産である。よって父は、長井家の経営する会社の資本を盤石にするため佐川の娘との見合い結婚を強制する。代助が縁談を断ると父は仕送りを止めた。つまり、独身の彼は、自分の意志で独身であり、自由なのだと錯覚していた。そして、錯覚のなかで、屁理屈をこねくり回していたのだが、独身も一家の財産目録の一つに過ぎなかった。
代助の錯覚は、家族の『情緒的きずな』に由来している。『菊と刀』にはアメリカ人とは違った日本独特の対人行動における基準が解説されている。
日本の家庭にゆるぎない情緒的きずながあり、それが受け入れられているという事実である。日本の家庭には非常に強い連帯意識がある。
(『菊と刀』 光文社古典新訳文庫P.99)
代助と父の『情緒的きずな』は、共有の資産という基盤の上で成立している。嫁いできた兄嫁、梅子には、その構造が痛いほどよくわかっている。ただ、梅子は、そういっても嫁いできた立場上、代助の自由(こんなものは錯覚に過ぎないのだが)を尊重して、この家族と代助の間の緩衝材の役割を引き受けている。
漱石は、幼くして養子に出され、家制度の理不尽を考えざるをえない生い立ちだった。また、日本の家族の非常に強い連帯意識が、個人に立脚した近代市民社会と相容れないことも見抜いていた。決断をして、「自由恋愛=三千代の不倫」を選べば、代助は家族との『情緒的きずな』を、バッサリと切らければならない。『自由』を選択して日本社会を生き抜いていくのは過酷だ。『門』はその過酷さを描いており、結局、「出家する(家族を捨てる)しか『自由』がないのだ」という悲しい事実が描かれている。
(おわり)
読書会の模様です。