
2017.9.29に行った村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』読書会のもようです。
私も書きました。
「井戸でやり過ごす」
保守とリベラル(革新)の対立軸というのが、日本の戦後政治を動かしていたが、2017年10月になって、その対立軸がそもそも仮象だったと思わざるをえない光景が広がっている。
『ねじまき鳥』の綿谷昇という人物は、まさに日本の保守政治家の欺瞞が凝縮したような人間だ。日本の保守の中には、戦前の朝鮮半島や満州での植民地経営に携わっていた政治家の流れを組む人たちがいる。日中戦争にも深く関わっていた人たちだ。
GHQの逆コースによって、ある流れをくむ保守系政治家たちは安全保障権益を隠れ蓑に反共保守というかたちで生きのびて、日本の戦後復興と繁栄を推進してきた。綿谷昇もまさしく、その流れにある政治家として描かれている。
綿谷昇の不気味さというのは、戦後保守の不気味さそのものだ。
「なぜ人間が戦争をするのか?」という問題について社会心理学者エーリッヒ・フロムの著作に、鋭い分析がある。
資本主義のある段階には、極端な能率主義(合目的主義・功利主義)が現れる。カント風に言えば「人間を目的としてではなく手段としてみる」傾向である。あるいは「最大多数の最大幸福」であり、人間を数=numberに還元する考え方だ。
生きた人間を手段として、つまり数としてみるというのは、つきつめれば、死体を数えるようなものだ。大量虐殺も、強制収容所も、無謀な総力戦による玉砕も、結局は生きている人間を死体と同じく数として捉える能率主義から生まれる。
好戦的な政治家は、死体愛好家に極めてよく似ている、とフロムは指摘していた。(『悪について』)
生きている人間の皮を剥ぐのも、バットで脳漿を飛び散らせるのも、人間を数として、あるいは、死体としてみていれば、造作のないことなのだ。国民を数として、有権者を数として、その数の足し算引き算で、政治を動かすこと。いわば、死体によるチェスである。
綿谷昇のような保守政治家が数の論理で動くと、政局は死体が踊りだす『かんかんのう』に似てくる。
暴力による抑圧と軍靴の跫音が脳裏にちらつく。
(おわり)
読書会の模様はこちらです。



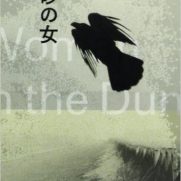
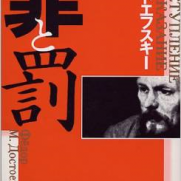





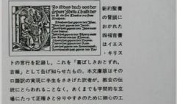

この記事へのコメントはありません。