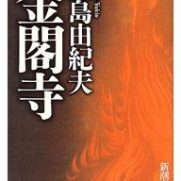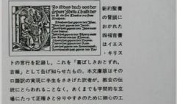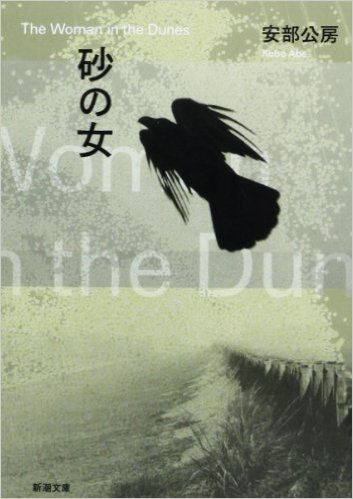
2019.11.8に行った安部公房『砂の女』読書会のもようです。
私も書きました。
「墓によって国家とつながる」
(引用はじめ)
あげくに、ここを離れられない理由は、ほかでもない、以前台風の日に、家畜小屋と一緒に埋められてしまった、亭主と子供の、骨のせいだなどと言いだす (第25章)
(引用おわり)
『無名戦士の墓と碑、これほど近代文化としてのナショナリズムを見事に表象するものはない。これらの記念碑は、故意に空っぽであるか、あるいはそこに誰がねむっているか誰も知らない。』(ベネディクト・アンダーソン 想像の共同体 P32)
骨を探したが見つからなかった。女が嘘をついているわけでない。土地が砂の力学によって移動し、それにつれて上モノの家も移動しているのである。墓がなくても、『愛郷精神=家族の思い出=ナショナリズム』は、人間の集団生活の営みのなかで持続していく。
『自由とは必然性への洞察である』とは、ヘーゲルの言葉であるが、人間の社会に自由などないのである。国家なしに近代人は生きられない。国家こそ必然性である。自由とは、国家と個人の切っても切れない腐れ縁への洞察だ。
部落を守るために、砂を掻き出さなければならない。そのためには男手の労働力が必要だ。砂の女にあてがわれた仁木順平は、当初監禁されて強制労働を課せられたと思った。市民社会の常識からすれば、そう思うだろう。
しかし、彼の中に、「より自由なはずの市民社会のほうが、精神的にはより不自由ではないか?」という疑問が萌す。自明だったものの必然性が、砂の中の不自由な生活で顕わになる。セックス一つとっても、市民社会では『商品見本』の交換である。セックスを媒介とした共依存関係が、婚姻届として役所に提出されているだけである。砂の中のセックスは原始的本能に由来していたが、それでもやっぱり、砂の外の散歩の交換条件として村人に見せつければ、それは、婚姻届の役割を果たすのである。
人間の生きる目的は社会秩序を維持することである。セックスも死の欲動も、市民社会では法のもとに管理されている。市民社会そのものが法体系である。人間は、元来、砂粒のような存在である。人間関係は、砂の流体力学と同じような自然の法則に支配されている。それを人為的な法則でさらにしばれば、近代市民社会だ。男と女は本能によって、つがいとなり、文化によって、家族を形成し、労働によって、社会秩序をなし、墓によって、国家とつながる。
死んだ者への思いが、過ぎ去った時間を思い出させ、儚い希望が、慣性の法則にしたがって、未来への時間軸を延長していく。縄梯子が目の前にあっても逃げ出せないのは、ナショナリズムの陥穽が巧妙だからであり、砂の女が誘うからである。
(おわり)
読書会の模様です。