
2017.6.8に行ったトルストイ『二老人』読書会のもようです。
岩波文庫の『トルストイ民話集 人はなんで生きるか?』所収
私も書きました。
『死の刹那まで、愛と善行をもってその年貢を果たす』
お金がなければ巡礼には行けない。また、神に呼ばれていなければ、巡礼には行けない。
そういうことを書いた宗教小説だと思った。厳格な自己規律を守って暮らしているエフィームに比べてエリセイは、嗅ぎタバコをやめられないなど、少しだらしないところがある。エルサレムは、キリストが十字架にかけられ、3日後に、復活した土地ではある。ロシア正教など、東方教会系のキリスト教徒がいまもなお、巡礼に出かけるそうである。とりわけ、キリストが埋葬された《主のみ墓(聖墳墓教会)には、今でも多くの信者が訪れる。
エリセイは、貧困家族を助けるため、巡礼を諦めたが、彼の生き霊が、《主のみ墓》に現れたのをエフィームは目撃した。
生き霊現象は、現実に起こりうるのか?
エフィームが、教会で見たエリセイの神々しい姿は、彼の変性意識(催眠状態)がみさせた、幻覚ではないのか?
巡礼を通して、個性が顕在化する。エフィームの厳格な規範意識も、エリセイの隣人愛の実践も、その人の信仰の個性なのであって、どちらに優劣があるわけではないと思う。
エーリッヒ・フロムは愛するというのは人の可能性を信じることだ、と述べた。
旅僧をうとましく思うというのは、人の可能性を信じきれない、エフィームの弱さである。エリセイのふくろや脚絆にしがみつく子どもたちの夢というのは、隣人愛を実践しきれない彼の弱さを責めている
巡礼の途上で、信者は克服しきれない自己欺瞞に向かい合う。日常生活のルーチンの中では決して、掘り下げることのない自己正当化の罠を自覚する。
信じることは難しいことだ。貧困家族を助けなければ、エリセイは、信仰を見失っていただろう。
いっぽう、エフィームも、エルサレムにたどり着いたのはいいが、帰途に、貧困家族の歓待を受けることで、手段が目的となって信仰を見失っていたことを自覚した。
信仰の危機の中で、彼らが共鳴し合ったとき、彼らの間だけに生き霊という現象が起こったのだと思う。
(おわり)
読書会の模様です。
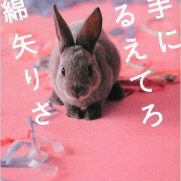
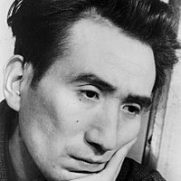
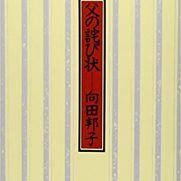
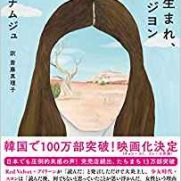
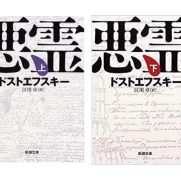

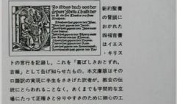
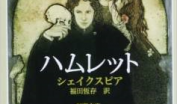
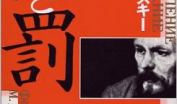

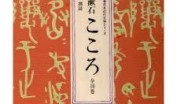
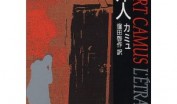
この記事へのコメントはありません。