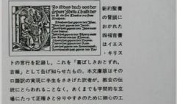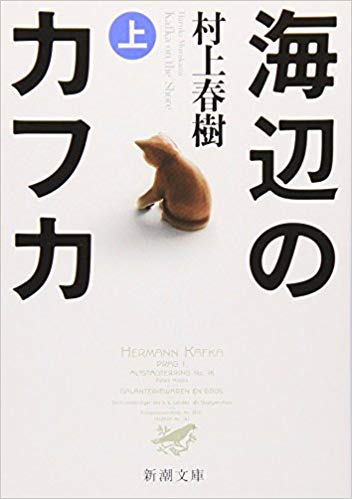
2019.9.27に行った村上春樹『海辺のカフカ』読書会のもようです。
私も書きました。
『猫笛と抑圧の移譲』
改めて読んで、直観したことがある。それは、四国の森で三八式歩兵銃を持った旧日本兵の現れるシーンであった。田村カフカの「田村」は、大岡昇平の『野火』の田村二等兵に由来するのではないか? 冒頭の山梨県のキノコ狩りのエピソードに出てくる女性教師の夫は、フィリピンのルソン島で戦死している。あの夫と田村カフカが現実の中で、半分ずつの存在を共有しているのではないか。
戦争によって離れ離れになった夫婦、田舎に学童疎開してきた少年時代のナカタさん。総力戦遂行により兵力動員、労働力動員が行われ、集団学童疎開によって家族の成員がバラバラに解体されたと『アジア・太平洋戦争』(岩波新書 吉田裕著 P.209)では、指摘してされている。ナカタさんの家も解体した。田村カフカの家も、母と姉が家出して、家族が解体している。
そして、家族の解体のあとには、個人の意識の解体がある。カラス、ルソン島で死んだ女教師の夫、ナカタさん、佐伯さんの恋人は、それぞれ、プラトンの『饗宴』の(男男・男女・女女)ように、田村カフカの、もとは対存在だったもう一方ではないのか。それがどこかで解体して、もとの対存在に戻ろうとして、苦しんでいるのではないか?
『母に捨てられた』という被害意識が 田村カフカには、わだかまっている。その喪失感は、次の段階では、怒りの発作として現れ、彼は、ときどき我を失う。このことは、家族が解体の次には、個人の解体があることを示しているかのようだ。家族の解体と個人の意識の解体は、すべて先の戦争とその記憶に由来するというのが、『海辺のカフカ』のテーマだと感じた。
ジョニー・ウォーカーは、猫を殺して、笛を作る(上巻P.297)。その笛は、魂を奪う。人間は、家族も個人の意識も解体され、社会から追い詰められれば、魂を奪われ、うつろな人間になる。彼らは、笛の音を聴くたびに、平気で弱いものをいじめ、なぶり殺しにして、最悪のケースでは、お互いに共喰いし出す、のではないか。
政治学者、丸山眞男が『超国家主義の心理と論理」で概念化した「抑圧の移譲による精神的均衡の保持」である。超国家主義は、人間から、主体的決断や、内面の自由や、私的領域を抑圧し、うつろな人間を作り出す。このうつろな人間こそが、総力戦に献身するのだ。
犬笛(ドッグ・ホイッスル)という言葉がある。犬にしか聴こえない高音域の笛の音のことだが、ある特定の人間の心だけにグサグサ刺さる差別的な表現を指す。猫を殺して笛を作ることにどういう意味があるのか? 人間社会の抑圧の移譲は、まずは犬猫などのペットの虐待から始まり、次に子供や女性、社会的弱者への暴力や差別として表れる。その最終段階が侵略戦争であり、絶滅収容所であり、ホロコーストである。
右傾化する社会では、ある政治家は、犬笛を使い、特定の有権者の支持を集めるために、目に見えない形の差別を行うという。猫が殺されるような社会は、必ず、猫を殺すような犬笛が吹かれている。『海辺のカフカ』が書かれた少し前の、1997年に神戸連続児童殺傷事件があった。少年Aは、田村カフカのように問題を抱え、日常的に猫を虐待し、殺していた。
猫を殺すような「抑圧の移譲」は、結局は戦争やホロコーストにつながっていくという危険を、この小説は、警告している。いくつかの兆候が、現象として表れ、社会的事件にまで発展し、法律が改正されるという段階を踏んで、自由の制限や差別や排外主義も、やむを得ないという空気が醸成されていく。ジョニー・ウォーカーの猫笛は、今まさに、現代の日本でも鳴り響いている。うつろな人間の耳には、心地よく響いているかもしれない。
心がうつろな人間こそは、猫笛に操られ、差別や虐待によって「抑圧を移譲」する。そうならないためには星野さんのように思い出の中の人間関係を振り返ったり、読書したり、ベートーヴェンを聴いたりする心の余裕を、忙しい生活の中でも確保しないといけない。忙しない社会生活では、現代日本人は、どんどん心がうつろになってしまう。「入り口の石」は、心のうつろな場所への通り道を塞ぐための石なのだろう。まずは、猫を虐待から救えるだけの心の余裕が必要だ。
(おわり)
読書会の模様はこちらです。