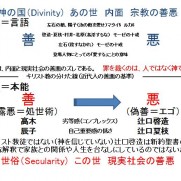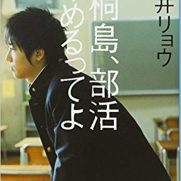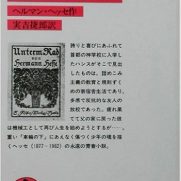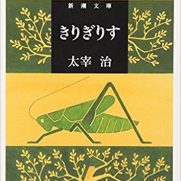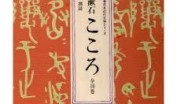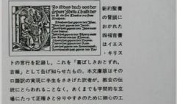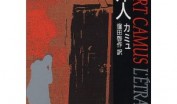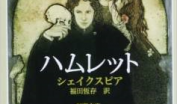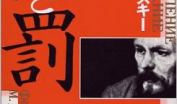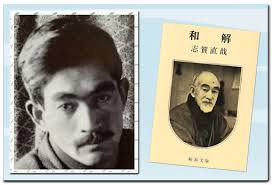
2017.11.17に行った志賀直哉『和解』読書会のもようです。
私も書きました。
「川の流れのように」
無縁仏というのがある。供養する親戚縁者のいなく成った死者や霊魂のことを指す。
父と長男が仲違いしたままであると、家系が途切れてしまう。これは、二人だけの問題でなく、末代までに因果をなす。
もし、「和解」しなければ、麻布の家と、順吉の家は、やがて疎遠になっていくだろう。
かつて一つの流れだったものが、二つに分かれて、別個のものになっていく。
慧子の死というのは、やがて順吉の血筋の途絶えること暗に示している。
自分は祖母と話していた。祖母は背が丸く、自身の膝に覆いかぶさるような恰好をして煙草をのんでいた。其所に康子が眼を赤くした儘出て来た。康子は祖母の前に来て坐ると、いきなりお辞儀をして震え声で、
「お祖母様、御免遊ばせ」と云った。
祖母は前からの姿勢で下を向いた儘、煙管の吸口を銜えて黙っていた。祖母の脣は震えていた。
自分はその時、赤児の死で祖母に不愉快を感じた自分を恥じた。
父と長男の確執がなければ、祖母は、東京に慧子を連れて行く無理などしなかった。
慧子が、電車の揺れのために死んだのは、一重に、順吉の意固地のせいである。
順吉は、どこかで、祖母が慧子の死の責任の一端を負っていると思い、不愉快を感じていたのだが、その因果は、自分と父との確執が発端であると、ようやく思い至ったのだ。
だから、「自分を恥じた」のだ。
祖母は、煙管を銜えて何を思っていたのか?
かつて一つの流れだったものが、二つに分かれて、別個のものになっていく。
おそらく、祖母の強いまなざしは、その分岐を見ていた。
慧子の死は、調和か、無縁仏かを暗示する出来事だった。
しかし、次女に祖母の名前からとって「留女子」と名付けたことで、父と息子は『和解』という一つの流れに調和した。
家族の不和が昂じて、流れが途絶えていくのは、夏目漱石の『それから』『門』『こころ』のテーマである。
家族の涙は、和解によって、しかるべき流れがもたらされたゆえである。
(おわり)
読書会の模様です。