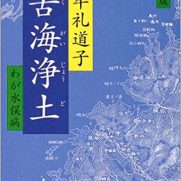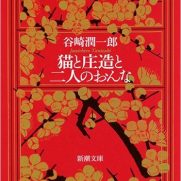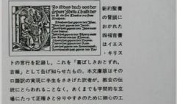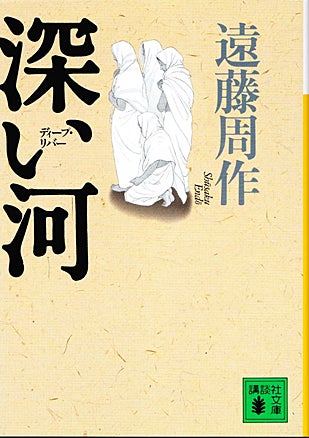
2020.1.17に行った遠藤周作『深い河』読書会のもようです。
私も書きました。
「生命の過剰と形式」
『深い河』の大津に『沈黙』のキチジローの面影が重なった。信念はないが、さりとて俗世にも埋没できない者の信仰を描いている。大津は、信じきるには弱すぎるが、信じずに生きていくこともできないというジレンマを生きている。行き倒れて亡くなったものをガンジス河のほとりで焼き、散骨するという仕事に従事をしながら、娼家にも通うという矛盾した行動に、道徳上のジレンマが現れている。
彼の抱えるジレンマとは、一体何なのだろう?
『沈黙』に登場した、転びバテレンのフェレイラは『この国は沼地だ」と喝破した。(新潮文庫『沈黙』P.230)
どんな神への信仰も、日本では根づかない。なぜならば、欧米のような形式を持たない文化的土壌だからだ、と指摘しているのだと思う。政治学者丸山真男は、全共闘の学生活動家に「形式的学問だ」と非難されてとき「文化とは形式だ」とやり返した、という。戦後の日本文化において、形式は、未熟な玉ねぎのままなのだ。文化の形式が持続しているのが伝統だとしたら、戦後の日本は、まだ戦後にふさわしい形式を持っていない。あるのは、人間の生命を、維持するためには十分な、空虚な豊かさだけであり、その生命の過剰を皆が持て余している。現代の日本人が、せいぜい持っているのは、「家」と言う形式である。これは玉ねぎのような形式だ。近代以降、家族や個人は、家という形式に束縛され、生活を営み、それが、国家の土台支える政治的結合の最小単位になっていた。しかし、現代の日本社会は、戦前の国民の主体性をのみ尽くす超国家主義の沼地から、個人主義をベースとした民主政治に移行している。だから、家は、もう戦後精神の形式たりえない。それは、磯辺や美津子の家庭生活の空虚が証明している。家という玉ねぎは「愛の働く塊り」(P.104)ではない。
(引用はじめ)
「何のために、そんなことを、なさっているのですか」
「え」
修道女はびっくりしたように碧き眼を大きくあけて美津子を見つめた。
「何のために、そんなことを、なさっているのですか」
すると修道女の眼に驚きがうかび、ゆっくり答えた。
「それしか……この世界で信じられるものがありませんもの。わたしたちは」 (P.350)
(引用終わり)
修道女は、信仰の形式を生きている。『死を待つ人の家』に暮らし、行き倒れの人を保護し、埋葬している。最期まで、人間の生命の尊厳を大切にしたい、どんな人間もせめて人間らしく死なせて、冥福を祈ってあげたい、というのが、彼女たちがこの世界で信じていることの核心である。インドのカトリックは、その核心に見合う信仰の形式を、インドのカースト制社会のなかに創造し、彼らの信仰を根づかせた。輪廻の予言を残して死んだ啓子も、塚田を看病したガストンも、沼田を慰めて死んだ九官鳥も、戦後日本の新しい形式の創造を暗示する、玉ねぎの使徒である。全く平凡で善良な存在が玉ねぎの使徒である。彼らが登場人物を人生の節目に現れ、玉ねぎとしてはまだ未熟な戦後日本の精神的形式に、質的変化を働きかけるために、「深い河」へといざなう。
美津子の記憶にある大津の学食のカレーの臭いのする吐息、そして、彼の詰襟からもれる汗の臭い。それらは、形式からはみでてしまう生命の過剰だ。美津子の性的な自暴自棄も、古い形式からの逸脱だ。沼地に繁茂する生命の過剰に、形式を与えるには、まず、信じる力が必要だと、狐狸庵先生は説いているのかもしれない。
(おわり)
読書会の模様です。