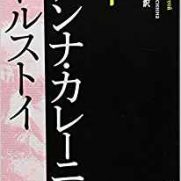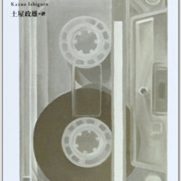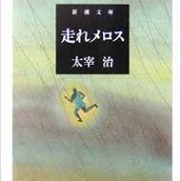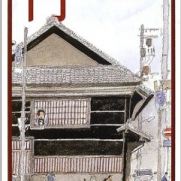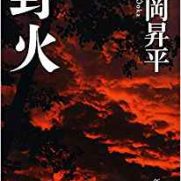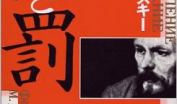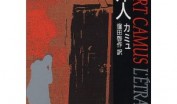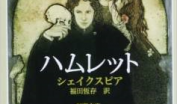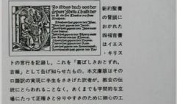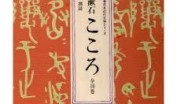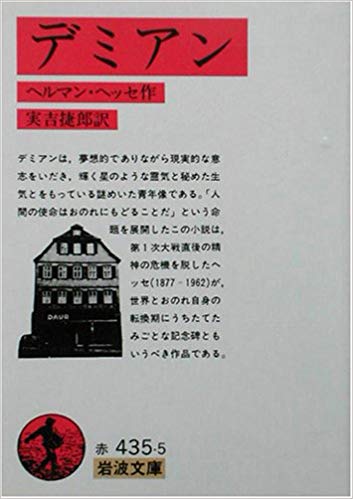
2019.5.24に行ったヘルマン・ヘッセ『デミアン』読書会のもようです。
私も書きました。
『自己形成 自己とは偶然か必然か、特殊か普遍か?』
カントの『判断力批判』に『合目的性』という概念がある。『合目的性』は『概念の原因性』と言い換えられる。例えば、「人間の生命」は、一つの概念だ。その概念の原因、つまり人間の生命の原因は、「偶然or必然」、「特殊or普遍」、どっちなのか。それが問うのが「原因性」である。主観的には偶然であり特殊、客観的には必然であり普遍的だと、考えられるのが人間の生命だ。
主観的に人間の生命が偶然の産物で特殊だとすれば、それをどう意味づけるのか? これが「生きる意味を問うこと」であり、生きる意味を自発的に獲得し確信を深めるのが「自己形成」である。プレモダンあれば、人間の生命は、創造主の思し召し(神による自己形成)であるが、近代以降の人間は、神に頼らず、自己のみで生きる意味を問いながら、自己形成するようになった。「カインのしるし」というのは、神に頼らない自己形成の比喩だ。
現象の世界で自己形成するには、生きる意味を問い続けるプロセスが必要になる。『デミアン』にはシンクレールの自己形成が描かれている。デミアンやエヴァ夫人というのは、シンクレールが生きる意味を問うためのプロセスである。だから、妄想の産物のような、現実感のない人々だ。
生きる意味を問うというのは、抽象的な作業だ。自己形成は徹頭徹尾、自己の抽象化の作業である。交尾して、子孫を残すだけなら、猿と同じで、生活圏内の環境への適応を目的とした具体的な自己形成だけで存在できる。だが、広範囲に社会秩序を形成する近代人は、より複雑な自己形成を求められる。パパとママのいる安全な家庭だけでは自己形成できない。クロオマアを通じて、一つしかなかった世界が、シンクレールの前で、「光と闇」の二つの世界に分岐していった。
なぜ、生きる意味を問うのか? それは、人は、例外なく死ぬからだ。現象として生成し、消滅するには、なにか目的があるのではないかと考える。目的を考えざるを得ないのは、すでに人間がすでに存在してしまっているからだ。矛盾した二つの世界に住めばなおさらだ。あとは、自己が偶然か必然か、特殊か普遍かを考えることになる。「概念の原因そのものを問うこと」を『合目的性』と名付けている。自己形成は、自己の原因そのものを問うことだ。つまり、「運命と心情(の原因を問うこと)は、(合目的性において)同一の概念(の主観的な問いそのもの)である」(P.144)
自己形成は、徹頭徹尾、主観的な、自己の抽象化の作業だ。人間の生命という概念を、自分で意味づける作業。要するに、自分探しである。
通常は、主観的な「生きる意味」の獲得なり挫折なりを通して、社会秩序に妥協ないしは、適応して自己形成は終わる。この作品では、デミアンやエヴァ夫人のユング的な心理学にサポートされてシンクレールは自己形成を成就する。一方、信仰やイデオロギーに頼って自己形成すると、やがて各所に軋轢が生じて戦争になる。第一次大戦とは、欧州の近代国家が選んだ帝国主義という自己形成の物語の矛盾が引き金になっている。シンクレールの自己形成に、ヨーロッパ近代国家の矛盾が重ねられているのが、この作品のすごいところだ。
(おわり)
読書会の模様です。