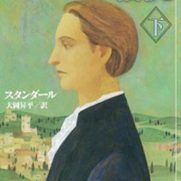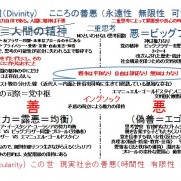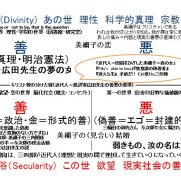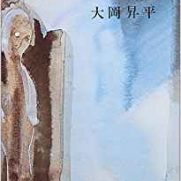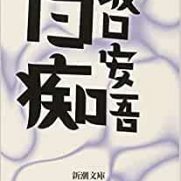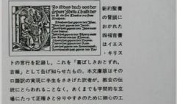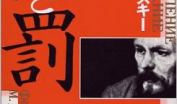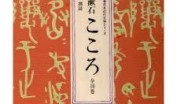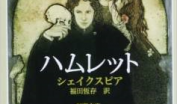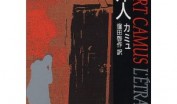2019.6.7に行った夏目漱石『三四郎』読書会のもようです。
私も書きました。
『広田先生は、デミアンじゃないのか?』
然るに原口さんが突然首を捩って、女にどうしましたかと聞いた。その時三四郎は、少し恐ろしくなった位である。移り易い美しさを、移さずにすえておく手段が、もう尽きたと画家から注意された様に聞こえたからである。 『三四郎』 10章
池の端で見た美禰子の姿が、三四郎の初恋であり、最初の美の体験である。「移り易い美しさ」を描くというのは、「有限」を「無限」にせんとする試みだ。近代の画家は、「有限」を「無限」にするという無謀な試みに一生を捧げる革命家のような存在だ。その意味で、詩人も、画家と同じく革命家だ。ただ、批評家は違う。批評家は革命を語るだけだ。
広田先生は、夢で再開した永遠の少女と『僕が女に、あなたは画だと云うと、女が僕に、あなたは詩だと云った』という会話を交わす。広田先生は、少女から『あなたは詩』だと言われたわりには、自分は散文的だと任じている。三四郎は、広田先生を批評家だと思っている。そして、三四郎は、詩ではなかった。駝鳥のボーアを考えていた美禰子は詩人だ。美禰子は、ごく保守的な見合い結婚をした。彼女は、イプセンのノラでもなければ、マダム・ボヴァリーでもなかった。
広田先生は夢の中の森を彷徨っていた、そこへ、三四郎が訪ねてきたので、夢から覚めた。そして最後の『森の女』の絵である。それは、池の端ではじめてみた美禰子の姿だった。三四郎も、いつしか、夢の中で森のなかに居る永遠の23歳の美禰子に再会するかもしれない。
美禰子と広田先生と三四郎の関係は、『デミアン』のエヴァ夫人と、デミアン、シンクレールとよく似ている。彼らにはお互いだけの無意識下での精神感応がある。慌ただしい都会の生活の中でも、ある人間関係の中では、濃密な無意識のつながりが営まれている。京都から乗って来た女も、池の端に立っていた美禰子も、轢死した女も、無意識の中では『森の女』につながっていく。原口が、覗き込んだモデルとしての美禰子の目の奥にも『森の女』が立っている。
三四郎は、ゆくゆく広田先生のような批評家になるのではないか? 批評家は、革命家ではない。「ミネルヴァの梟は迫り来る黄昏に飛び立つ」とはヘーゲルの言葉だが、畢竟、批評家の芸は、後出しジャンケンの話芸である。
滅びるね。危ない、危ない。
三四郎も、いずれは、汽車の中で未来の三四郎を脅すかもしれない。水蜜桃を食べて、ニヤニヤしながら。
(おわり)
読書会の模様です。