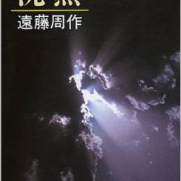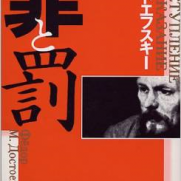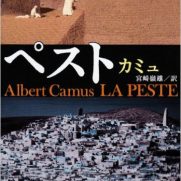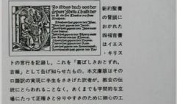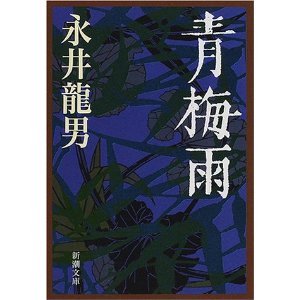
2019.2.8に行った永井龍男『一個』読書会のもようです。
私も書きました。
「左右に揺れる一個人」
月給取りをサラリーマンと呼び、女性賃労働者をOLと呼ぶ。階級というむきだしの社会的諸関係が、横文字にされることで、おおいかくされる。夏季闘争を戦う側と防ぐ側に、人間は分かれる。月給取りは前者に、経営者側は後者に。ただ、所属や役職を剥ぎとれば、一個人が、野ざらしにされて、立ち尽くすだけだ。
定年を二ヶ月後に控えて、この佐伯は、途方に暮れる。彼の精神は、長年のルーティーンによって摩耗減損している。再就職のあてはなく、娘は嫁ぎ先で危篤。家運は、柱時計が心配して口をきくまでに、傾いている。
ドイツの写真家、マイケル・ウルフの撮った東京の風景。満員電車にギュウギュウ詰めにされて、雨に曇った窓ガラスに浮かび上がるサラリーマンは、苦悶に喘ぎながら祈るような切ない表情である。見ようによれば、あれは、まさしく「エンゼル」である。戦後日本の競争資本主義のために生まれた無垢なエンゼルたち。
年金や社会保障などの「おくるみ」があれば、エンゼルのような無垢なサラリーマンは、とりあえずは安心だ、今は、手厚くおくるみに包まれて育てられている赤ん坊たちも、いずれ、立派なエンゼルになって満員電車の吊り手に手をのばすだろう。しっかりつかまれば、目的地まで、誰かが連れて行ってくれる。「労働は人間を自由にする」という看板のある建物に?
葬儀屋の前を息を止めて通り過ぎる。人間は、「死」を知っている。人間は、エンゼルではない。エンゼルは神の使いであり、もとは聖霊だ。聖霊は死なない。人間は動物だから、やがて死ぬ。魂は死後も生き続けるのだろうか?
定年後も、再就職という吊り手を掴めなければ、生きていけない。つまり、つかまる吊り手がなければ、一個人の一番もろい処を、絶え間なく小突いてくる、柱時計と向かい合わなければならない。左右の政治体制に揺られながら、戦後日本社会を支えてきたエンゼルたちがいる。それぞれが『一個』の魂を擦り切らせながら、今日も吊り手をしっかり握りしめて、左右に揺られる。柱時計の振り子のように規則正しく揺れながら。
(おわり)
読書会のもようです。