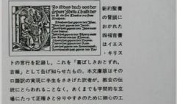2019.10.11に行った岡本かの子『河明り』読書会のもようです。
私も書きました。
『青春の孤独と纏縛(てんばく)』
旧家の束縛から逃れて南洋に繰り出す木下は、戦前の日本の鬱屈を象徴しているように感じた。没落していく旧家と、その反動として超国家主義のもと膨張していく大日本帝国。
1942年2月15日大英帝国の植民地であったシンガポールが陥落した。1945年9月12日まで日本の統治下におかれた。
それは嫌やだと同時に、またどうしても憎みきれないものがある。家というものに護らせられるように出来ている女の本能、老後の頼りを想う女の本能、そういうものが後先の力となって、自分でも生むと生まないとに係らず、女が男の子というものに対する魅着は、第一義的の力であろう。
南洋の島々の半音ない爛漫とした自然は、眠いだろう。しかし、一方、四季につれて移調する日本の自然は、その半音の反響ゆえに息苦しいのかもしれない。過去の歴史は、その息苦しさからの解放を戦争に求めてしまったもではないか?
だが、こう思いつつ私が河に対するとき、水に対する私の感じが、殆ど前と違っているのである。河には無限の乳房のような水源があり、末にはまた無限に包容する大海がある。この首尾を持ちつつ、その中間に於ての河なのである。そこには無限性を蔵さなくてはならない筈である。
井伏鱒二の『黒い雨』の後半、原爆のあとの街を背景に、海から河に遡るうなぎの稚魚の描写がある。無限に包容する海と、無限の乳房のような水源を行き来することに例えられているのは、群生秩序として、まるで一つの生き物のようにうごめいている日本社会の宿命そのもののような気がした。
温帯湿潤気候で島国の日本には、共同で財産を管理する家制度や、その延長線で忠君愛国親孝行の儒教的な徳治主義やら、血縁や官僚的人事からなる人治主義やらの纏縛(てんばく)が常に伏在している。そして、定期的に、台風や地震など自然の脅威になすすべなく翻弄されている。
宙ぶらりんの浪人時代であった私も、予備校の帰りに荒川の土手で仄かな河明りを眺めて、長い時間、たそがれていたことがある。河明りの秋の日差しの強い反射が、青春の孤独と纏縛の象徴として、今も忘れられない。はるか隣には、いちゃつくカップルがいた。南洋なら鰐に食われていただろう。あの河明りの強い印象は、今も脳裏に焼き付いている。
(おわり)
読書会の模様です。