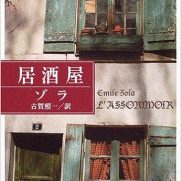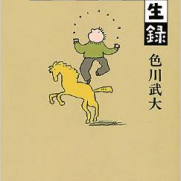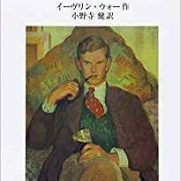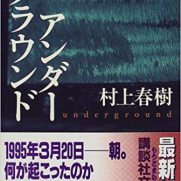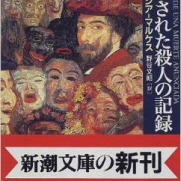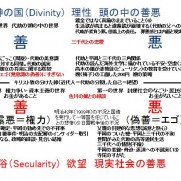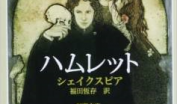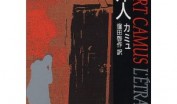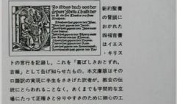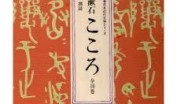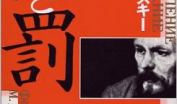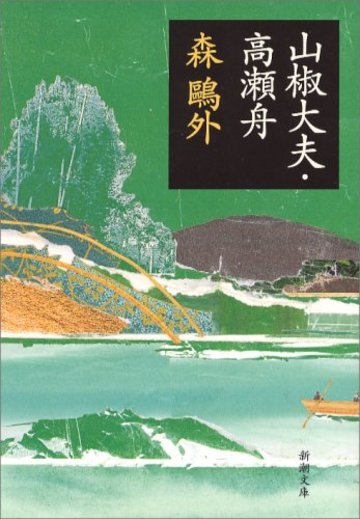
2019.2.22に行った森鷗外『高瀬舟』読書会のもようです。
私も書きました。
『安楽死は帝国への不正行為』
庄兵衞の心の中には、いろいろに考へて見た末に、自分より上のものの判斷に任す外ないと云ふ念、オオトリテエに從ふ外ないと云ふ念が生じた。庄兵衞はお奉行樣の判斷を、其儘自分の判斷にしようと思つたのである。さうは思つても、庄兵衞はまだどこやらに腑に落ちぬものが殘つてゐるので、なんだかお奉行樣に聞いて見たくてならなかつた。
生きていても、右から左に収入が流れてしまい、いっこうに生活の基盤を築けない最下層の労働者、喜助。彼は、弟の自殺を幇助した罪で、200文をお上から渡され遠島に処された。所払いである。
落語『時そば』のまくらで『客二ツつぶして夜鷹三つ食い』という川柳が紹介されるケースがある。現在の人権意識に照らすとアウトな句だが、夜鷹(街娼)が、客を2人とって48文。夜鳴きそばが、1杯16文なので、客2人で、そば3杯ということだ。
200文は、そば13杯分。現代なら1万円程度か。だとすれば、その程度のまとまった金でさえ、夢のようだと幸せに浸る喜助の生活ぶりが哀しい。都市の無産階級のその日暮らしぶりが伺える。
ドイツ帝国の鉄血宰相ビスマルクによる『アメとムチ』政策は、労働運動や社会主義運動を厳しく弾圧する一方で、社会保障制度によって国民を懐柔した。森鷗外が、まさにドイツに留学していた1890年代の出来事だ。
第一次大戦のさなか、社会主義運動のたかまりを肌で感じて、その対応策を為政者の側として考えた森鷗外の苦悩が伺える。オオソリテエ=政府が、アメとムチで統治の手綱を引き締めなければ、無産階級である喜助の権利への目覚めは、社会主義運動を燃え上がらせる。第一次大戦のもたらした社会矛盾が、ドイツ帝国を崩壊させた。(1918年ドイツ革命)
鷗外の周りには、石川啄木のように『時代閉塞の現状』(1910年8月)を訴えた若者が出入りしていた。独占資本と強権国家の帝国主義体制が、無産階級の若者の希望や生命を圧殺する社会の現状を、為政者側の森鷗外なりに案じた小説だと思う。
アリストテレスは、「自殺は、国家に対する不正である」と説いた。(『ニコマコス倫理学』)帝国支配下においては、国民の命も所詮は、お上からの預かりものだ。自殺も安楽死の自由も許されない。庄兵衛の権威(オオトリテエ)主義に、鷗外の帝国軍医としての権威主義が重なる
(おわり)
読書会のもようです。