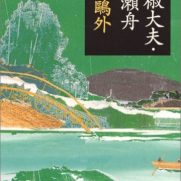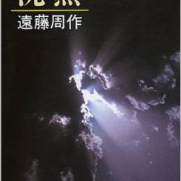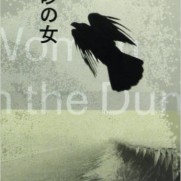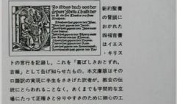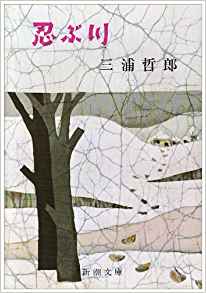
2018.5.4におこなった三浦哲郎『忍ぶ川』読書会のもようです。
私も書きました。
「暗い血 汚れた血 そして親孝行」
主人公の私は、自分の六歳の誕生日を境に一族が衰運を迎えたことを気に病んでいた。兄姉が相次いで自殺したり、失踪したりした。家と血のつながりが、手枷足枷となって運命を縛っていた頃の話である。
『忍ぶ川』を読んで、嫌だなあと思った。このジメジメした日本文学の私小説特有の情念が、隅々までわかってしまうので、余計に嫌だ。
逐電した兄も、おそらくえいかっこしいだったのだ。一族から借金して身をくらませた。つじつまがあわなくなると、どこかに消える。そうだ。そうなんだ。下手くそ。身勝手に死んだり失踪したりする肉親がいて、この男は、その暗い血におびえて生きる無力感に耐えられず、志乃という女性を道連れにした。
無力感とナルシシズムで志乃を口説いたとしか思えないのだが、でも、輪郭のくっきり、詩情あふれる文章で綴られていて、すいすい読んでしまった。
「人はなんで生きるか?」「自由とはなにか?」そういう主題の話ではない。つじつまが合わなくなれば、自殺したり失踪したり、こんな選択肢しかないという戦後間もない日本の社会の現実が、丹念に描かれているだけだ。
貧困、絶望、不条理との戦いが描かれているわけではない。両親の死ぬ前に結婚して安心させてやりたい、でも、経済原理は無視、という親孝行が描かれている。ただ、とても幼い男女の純粋としては美しい。
太宰や安吾が、家庭を呪詛して、親を呪って、小説を書いたのを思えば、なんてナイーブであろう。ナイーブな保守反動文学だ。
日本文学の保守本流は、仏壇や葬式など、死者たちばかり書いている。志賀直哉の『和解』は、死んだ子供をどこに埋葬するのかという問題を描いた。川端康成の『雪国』は、死んだ恋人の墓を守りながら狂っていく美しい女を描いた。そんな話ばかり。
「死者は死者に葬らしめよ」という福音書の言葉があるが、そこからはじめてほしい。でないと、自殺者の自己欺瞞にとらわれ、無力感のなかで、はかなく衰弱していく姿こそ、日本文学だとなってしまう。嫌だなあ。
(おわり)
読書会の模様です。