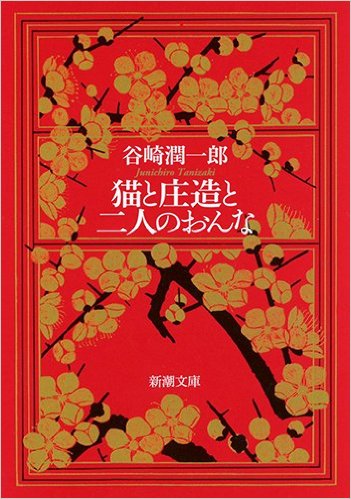
2017.3.17に行った谷崎潤一郎『猫と庄造と二人のおんな』読書会のもようです。
私も書きました。
『きょう、ママンが死んだ』
「お母さん、ちょっと頼みがありまんねん。―――」
毎朝別に炊いている土鍋のご飯の、お粥のように柔らかいのがすっかり冷えてしまったのを茶碗に盛って、塩昆布に載せて食べている母親は、お膳の上へ背を丸々と蔽いかぶさるようにしていた。
私は小学生の頃『たはむれに母を背負いてそのあまり軽きに泣きて三歩あゆまず』という石川啄木の短歌を読んで、感動して泣いたことがある。しかし、大学生の時、テネシー・ウィリアムズの『ガラスの動物園』という戯曲を読んで、主人公が、気位の高い母と、足の悪い姉の束縛に耐えられず家出してしまう結末のリアリティに納得した。啄木の詩の奥底には、日本の母への怖れが滲んでいるかもしれない。
庄造の母、おりんは、『いつでも結局この倅を思い通りに動かしてる』のだ。品子が追い出されたのも、福子が嫁いできたのも、おりんの計略があったからである。おりんは、老醜と妄執を悟られないために、塩昆布でおかゆのようなご飯を食べて、家の片隅に申し訳なさそうに生きているふりをしているが、その実は、この家を支配している。しっかりした品子より、家産があって、だらしのない姪の福子のほうが、自分には都合がいい。福子を近所の風よけにして、庄造を頼りない家長にしておくことで、おりんは、いつまでも奥の院に君臨するのだ。怖ろしいことだ。
母と福子の束縛に嫌気がさして、ヤケになって自転車を乗り回し、リリーに会いたくなって、空き地に佇む庄造は、哀れだった。
庄造は、母親からも女房からも自分が子供扱いされ、一本立ち出来ない低能児のように見做されるのが、非常に不服なのであるが、さればと云ってその不服を聴いてくれる友達もなく、悶々の情を胸の中に納めていると、なんとなく独りぽっちな、頼りない感じが湧いてくるので、そのために尚リリーを愛していたのである。
「息子はその母親の子どもであることだけで充分償っている。」(安岡章太郎『海辺の光景』)
(おわり)
読書界のもようです。

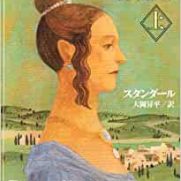









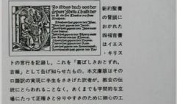
この記事へのコメントはありません。