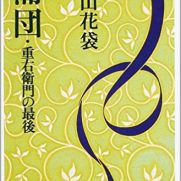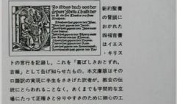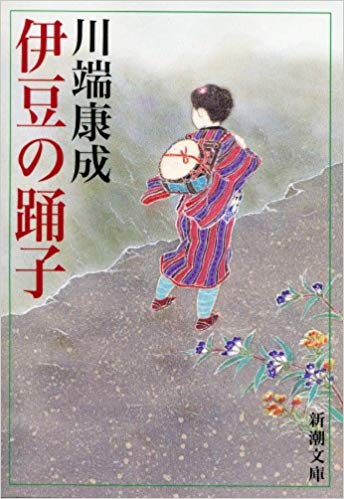

2019.12.27に行った川端康成『伊豆の踊子』読書会のもようです。
私も書きました。
「ショー・マスト・ゴー・オン」
天城峠の前までは、まるでストーカーのようなしつこさだった。『踊子を今夜は私の部屋に泊まらせるのだ』(P.12)という、鬱勃たる欲情。ロリペド大国ニッポンの旅情。それが「ポキン」と折れたのは、お茶を給仕して、真紅になりながら、ぶるぶる震える踊子の手付に、四十女が『まあ! 厭らしい。この子は色気づいたんだよ。あれあれ…・…』というきついツッコミゆえである。「私」は、人権意識のない俗情から目を覚まされたわけである。
一高生の制帽といえば泣く子も黙るエリートの証である。要するに、『水戸黄門漫遊記』の葵の御紋の印籠である。しかし、エリートでありながら己の孤児根性に苛まれる「私」は、反省に倦んで、メンがヘラって伊豆を旅している。こんなことは、旅先の人々は知らない。踊子も、無論知らない。でも、彼のメンがヘラってるのは、この一行は薄々知っている。
薫こと踊子は、一高生の「私」に思いを募らせていくが、彼女は、厳しい渡世の旅が宿命である。やっぱり、投げ銭を握って帰ってくる踊子である。要するに、櫛だって、犬の毛を梳いて、汚して、かんたんに形代にはしない。(兄貴の栄吉がその代わりに、口臭清涼剤「カオール」をくれた 半笑←)真っ裸で朝日の中を立ったり、眦に紅を残したまま見送りに来たりするような無意識の媚態と渡世のなかを踊子は生きている。
四十女が、「私」しきりに孫の四十九日に立ち会うように求めたのは、家族にならなければ、薫との関係を許すわけにはいかないという意味だ。栄吉が、始終なにげなく「私」のもとにやってきて、慣れて、なおかつ投げつけられた金包を、断ろうとするのは、彼なりの渡世の了見があるからである。四十女と栄吉のコンビプレー。栄吉はそれでも紋付きの礼装で「私」の船を見送った。爺さんを追い出して、楢山参りに連れてっても、「私」を大島に呼ぼうとする、四十女の浅ましさ。あてが外れて、急に冷たくなる四十女と千代子の夏目漱石の『こころ』の叔父さんのような仕打ち。畳み掛ける。
この一座のプロモーターたる四十女の世知は、栄吉のように、夫婦となって一座に同行して、共同生活することを、「私」に対して、暗に、求めている。それに反発して、「私」は旅情が同情に変わらないように、亡くなった子の花代だけ渡し、東京に帰るだけの世知があった。そこは、腐っても一高生である。太宰とは違う。薫という名前で表記されず、終始踊子であるのは、結局は、「私」にとっては最後まで踊子であったからだ。それも世知だ。世知辛いとはこのことだ。
吉永小百合や山口百恵で映画化されているが、私は、藤圭子さんのことを思い出した。藤圭子さんも両親が浪曲師で、旅回りに同行していたそうだ。芸能界の古い体質ということが言われる。最近の宇多田ヒカルさんをみて、私が世知辛さを感じるのはそこだ。ジャニーさんの言った「ショー・マスト・ゴー・オン(お座敷よ!毎日続け!)」。アメリカナイズされても、まだ日本の芸能の名残は深い。
千代子は、子供を早産で亡くしてもドサ廻りしてお座敷を続けなくてはならない。だから、芸能人は、安定と持続を求める市民社会の倫理になじまない。一般市民の知らない悲しみを隠して、踊子は、お座敷を続ける。
川端先生も、「物乞い芸人村に入るべからず。」を自らへの戒めとして生きていったように感じた。彼の選んだ道も、踊子の世界と同じである。
金歯だかジルコニアにしたほうがいい(P.37)という千代子と踊子の会話に、百合子が入っていないのがみそである。百合子は、この旅芸人一家の了見を、これまた雇女の世知辛さで、むっつり見抜いている。
市民社会の倫理が、以上のことを隠蔽すると、吉永小百合やや山口百恵主演の『伊豆の踊子』になってしまう。
孫を三人抱えて、水戸に帰る婆さんの悲哀は、踊子と「私」が一緒になったあとの四十女の未来を暗示しており、冒頭の薬の能書きの中に埋もれる中風の老人は、栄吉のこれからの姿だったのかもしれない。そして、隣に寝ている少年は、昨日までの「私」だ。
最後の涙は、世知が極まった衝撃と、所詮、そんな世知が、自然の智慧に抱かれてると悟ったゆえの賜物である。
(おわり)
読書会の模様です。