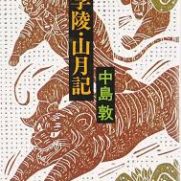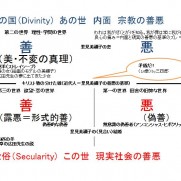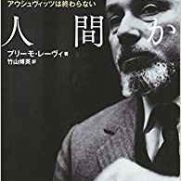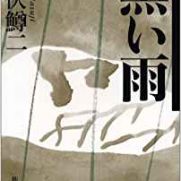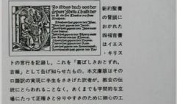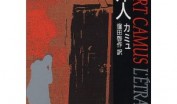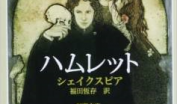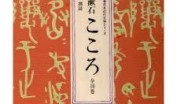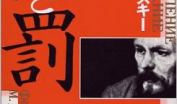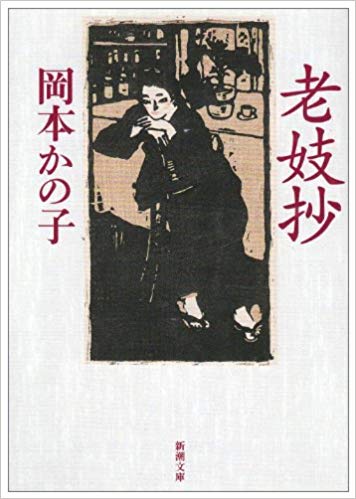
2019.1.18に行った岡本かの子『老妓抄』読書会のもようです。
私も書きました。
三界を自在に行き交う復讐の鬼
現実というものは、切れ端は与えるが、全部はいつも眼の前にちらつかせて次々と人間を釣って行くものではなかろうか。
資本主義の現実は、人間を釣っているところにある。投資の限界効率(the marginal efficiency of capital)とは、資本を1単位増やした時に得られる期待収益を指す。柚木に投資してパトロンになった老妓は、触るものみな金に変えてしまう能力を得たため、皮肉にも餓えに苦しんだといわれる伝説のミダス王のようであった。老妓が触れると、彼の大切なパッションが、みんなダメになってしまう。だから、老妓は自分の業の深さに、さみしさをおぼえる。焦がれてもどうしても手に入らないものが存在するジレンマに、老妓の飢餓感はますます募る。
苦労や苦痛がなければ、若い男の生きようとするパッションは形にならない。柚木の認識力を、老妓が直観的に麻痺させているように思う。老妓の親切は、柚木をふやけた出来損ないに変えてしまう悪意にかわる。その証拠に、出奔癖がついても必ず帰ってくる自堕落な習慣が彼の中に育ってしまう。
柚木の貧しさの中にある苦痛や苦悩こそが、彼の限界効率を高めるのだ。老妓は、苦痛や苦悩を認識する人間にこそ許された智慧の果実にたいして、まずもって復讐するのである。老妓の手になれば、柚木の男としての限界効率は崩壊する。それは資本主義への優雅な復讐かもしれない。
サディズム、支配欲、執着、『女三界に家なし』といわれるのはそれなりのわけがある。老妓は、鬼になりつつある人間だ。
人々は真昼の百貨店でよく彼女を見かける。
目立たない洋髪に結び、市楽の着物を堅気風につけ、小女一人連れて、憂鬱な顔をして店内を歩き廻る。恰幅のよい長身に両手をだらりと垂らし、投出して行くような足取りで、一つところを何度も廻り返す。そうかと思うと、紙凧の糸のようにすっとのして行って、思いがけないような遠い売場に佇む。彼女は真昼の寂しさ以外、何も意識していない。
老妓の正体は、三界を自在に行き交う復讐の鬼である。芸妓として老いて、なおますます自分自身になろうとする彼女の強情の絶望が、さみしい堅気のすがたを借りて、昼下がりをさまよう。
(おわり)